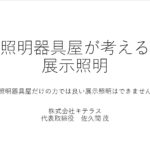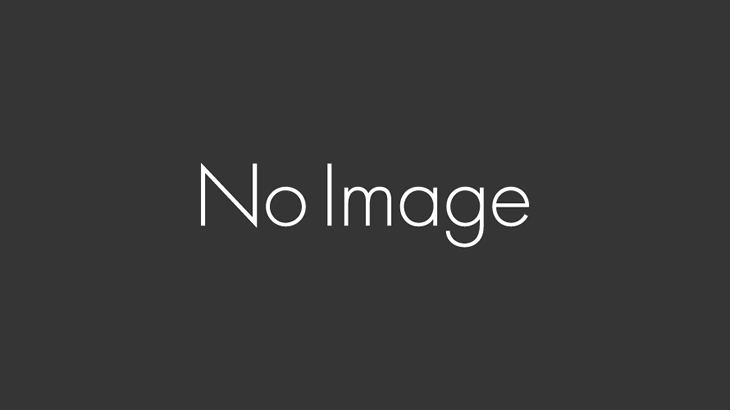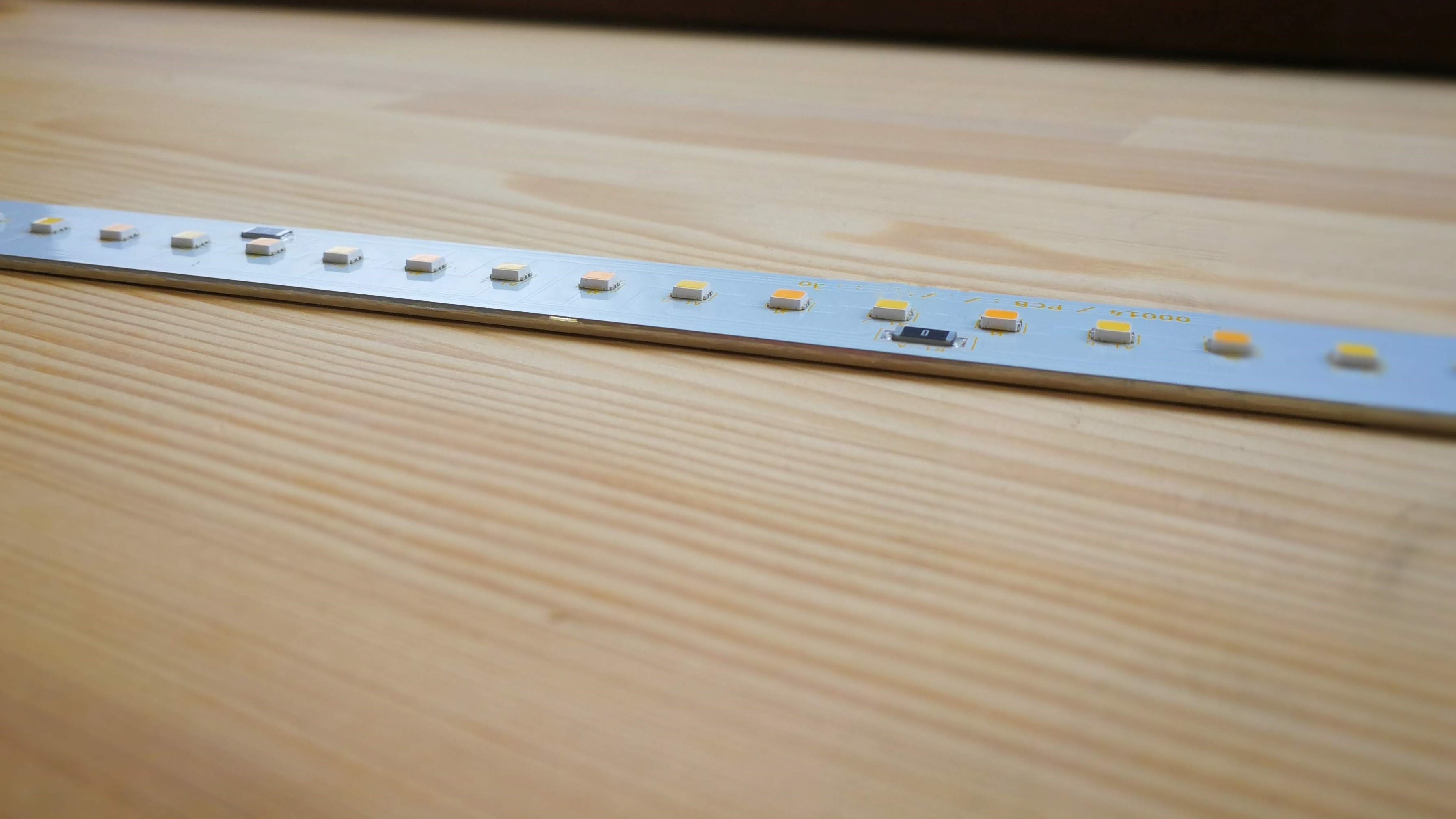先日訪問した美術館で展示品とほぼ同寸法、同質量の作品を実際に手にすることが出来ました。通常の美術館での経験とはちょっと異質で、なかなかの刺激がありました。
これと期を同じくして、先輩系友人から「美術館の照明は究極的にどうなるの?」みたいな質問を受けまして、つまらない事に「手法としては大きな変化はないのでは」と答えてしまいました。
この2つの事が、何となく気になり考えています。
世の中で液晶モニターが一般的になり、随分と月日が経ち、その解像度は既に人の眼の分解能を超えています。また、昨年くらいからVR技術も大きく普及しはじめました。
これらの事から、思ったよりも近い将来に眼でみるだけの美術鑑賞はVRの世界に行ってしまうのかなと想像します。
Google Art Project等はその走りかなと思います。
一旦デジタル化してしまえば、保存と鑑賞の相反は無くなりますし、視点や光の当て方はソフト上で如何様に出来るでしょうし、実物見るよりも満足感は高そうな気もします。目で見るだけの美術鑑賞の主流は移っていくのではないでしょうか。
触覚や嗅覚などは、なかなかデジタル化しにくいので、これらの五感を使うものだけがリアルな世界での活動として残っていくのかなと想像します。
そうなると、展示用の照明を作っている私の仕事は、この先も残っているのだろうか?とかなり不安になってきました。
どのような産業も、その社会に存在する他の技術との相対的な左様で栄枯盛衰があります。照明器具の産業は割と枯れている分野ですので、大きな変化は生じないものと高をくくっていたのですが、もしかすると私が仕事人生を全うする前に、展示用照明の産業が強烈に小さくなっているかもしれません。
平生の仕事をこなしている中にあっても、時々は立ち止まり、頭を上げて少し遠く見ておく必要があろうかと思ってきました。

こうして、実際にお茶を点てたりするなどの行為を通して得られる感覚の全てをVR化する事は出来ないと思います。
存在し続けるしぶとい仕事とはこうした分野なのでしょうか。
※美術館・博物館での照明を作ってみたい方を募集しています。
株式会社キテラスでは美術館・博物館で使われる照明器具を作りたい方を募集しています。
ご興味のございます方はこちらをご覧下さい。